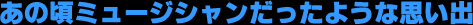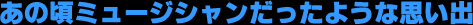| | つらかった。
音楽祭の楽屋に居ることがつらかった。
出番を待つその楽屋にいるだれもが、賞を狙って必死に最後の音合わせをやっている。
だがもうすでに決まっているのだ。
賞のひとつはぼくに決まっているのだ。
音楽祭の出る前、出たくないと英五さんに相談している。
だが英五さんの答えは、ぼくの予想と違って「出ろ」だった。
他の有名な音楽祭もみんな同じことをやっているのだから恥じることはないと、ぼくの知っている英五さんとは思えない答えが返ってきたのだ。
歌い終わり、台本通りにぼくの名が呼ばれる。
司会者がわざとらしく歓喜の声を上げてぼくをステージで向かえ、握手の手を差し出している。
ぼくは手を差し出すことなどできない。
とても喜ぶ顔などもできない。
トロフィーをもらうことが恥ずかしくてならなかった。
ステージの下には賞に落ちて肩を落とすアマチュアミュージシャンたちの姿が見えている。
早くこの場から逃げたかった。
「あまりの喜びに表情を失うほどシャイな田中くんでした」
そのような当時の司会の声をこの文を書きながら思い出した。
そして家への帰り道、ぼくは貰ったトロフィーを道に叩きつけたのだ。
トロフィーはいとも簡単に砕け散ってしまった・・・
それがぼくが音楽をやめるはじまりとなっていったのだ。
あのときなぜ音楽をやめようと思ったのか・・・
そうだ、当時は格好つけてその賞を貰ったことでイヤになったなどと言っていた。
だが違う。
英五さんがあのとき音楽祭に出ろといった意味、そしてあのとき音楽をやめようと思った本当の自分の気持ちがわかったのはずいぶん後のことである。 |
|
|
|
| | 自信がなかったのである。
プロとしてデビューをするというのに、賞をもらうことに自信がなかったのである。
あのとき最初から賞をもらうことが決まっている音楽祭に出ることを、英五さんは「恥じることはない」と言ったのはつまりはこういうことだったのだ。
自分に自信があり、自分の曲が歌が最高という矜持があれば、たとえ賞が決まっていたとしても、自分以外その賞を取るやつはいないと言い切れる自負があるはず。
どうせ自分が実力で取るのだから、最初から賞が決まっていようが関係ないということだ。
だがぼくには思えなかった。
ぼくよりも他のミュージシャンの方がうまいと感じていたのだ。
プロでこれからデビューしようとするミュージシャンが、自分にまったく自信が持てなかったのである。
そう、あのときぼくが音楽をやめようと思い始めた本当の思いは、プロとしてやっていく自信がなかったということだったのだ。 |
|
|
|
| | 渦が巻いていた。
この場所で一秒たりとも居たくないほどの憤懣がぼくの中で、そして周りで渦巻いていた。
今、ぼくがミュージシャンをやっていたことを知る友はほとんどいない。
この「ミュージシャンだったような思い出」を読んで、「そうだったんだ」と、「なぜ今まで黙っていたんだ」と友、知り合いたちから言われ、いくつもメールももらった。
なぜ30年近く隠すように誰にも話さなかったのか・・・
隠していたわけではない、記憶から消えていた・・・そう、消してしまっていたのだ。
そのことを「ミュージシャンだったような思い出」を書きながら思い出してきたのである。
忘れていたのではなく、消してしまった記憶。
それほどのことが、誰もが「やってられない!」と憤懣したいくつものことがあのときぼくの周りであったという事実。
スタッフをやったことで、以前から事務所のスタッフと飲みに行けば酔った中から出た裏での話しをぼくは知っていた。
アーチストには決して話さないような裏での出来事・・・
そんな中、「あのねのね」が事務所を辞めた。
そのことに関してもイヤな話しがいくつも耳に入ってきていた。
当時、事務所を支えていたスタッフSさん、Nさんが辞め、ぼくが事務所を離れるときには事務所で一番信頼していたスタッフのIさんまでもが辞めていく・・・
やはりこのときの渦の話しは辞めにしよう。
そのことを思い出すことで、あの時代の大事な思い出までもが汚れてしまう気がしてしまう・・・
そう、ぼくはあのときのある出来事がきっかけで、デビュー曲の歌入れでスタジオを押さえている日、スタジオには行かず「辞めます!」と、事務所に電話を入れたのだ。
そして当時、事務所から1円の金ももらっていなかったぼくは、深夜の東京駅から、大垣行きの各駅停車に乗って京都へと帰って行ったのである。
闇を走る各駅停車の中での気がかりは、まだ映画の撮影中だった英五さんにも黙って消えてしまったことだった。
それから1年半後、「ゴルゴダの丘」はそのときのオケで英五さんがレコーディングしていた。
英五さんのキーより1音半高いぼくのキーで造ったオケだったこともあり、サビの部分は原曲とは違う曲となっていた。 |
|
|
|
| | 毎日何度も電話が鳴る。
どこから掛かってきているかはわかっているが電話は取らなかった。
そのときぼくは必死に机に向かっていた。
絵を描いていたのだ。
あのときアマチュアからもう一度一からやり直そうとしなかったのは、つまりは音楽で生きていく自信がなかったということである。
だが前に書いたように、当時のぼくはそのことに気づいてはいなかった。
音楽は好きだったから、ライブハウスでは歌っていた。
だがそのバックで、スライドで机に向かって描いた絵を流してのライブである。
みんなに必死で描いた自分の絵を、歌うことで見てもらっていたのだ。
「ある」という漫画の同人誌も創り、その本は「ぱふ」や「プレイガイドジャーナル」にも取り上げられたりもした。
半年ほど経ったあたりから、事務所からの電話を取るようになったが、もう事務所とは距離を置いての付き合いでしかなかった。
以前のように無報酬で事務所の手伝いをするなどということはなく、生きていくためのバイトとしての付き合いである。
京都でアマチュアのコンサートを開き、ライブハウスで歌いながら、事務所からのビアガーデンのステージ、レストランバーでの弾き語りなどの仕事をバイトとしてうける。
普通のバイトも36種類にわたっていろいろやった。
事務所は京都に新しく造ったスタジオで、ギター一本で録ったぼくの曲をレコードにしてくれたりしたが、事務所へもどる気はもうなかった。
とにかくもがいていた。
毎日のように机に向かって絵を描き、そのもがきから必死に光を探していた。
そして1980年12月8日、ぼくはうだうだと引きずっていた音楽への未練を断ち切り、絵で勝負すべく東京へ出ると決めた。
ぼくが尊敬していたミュージシャンのジョン・レノンが殺された日だった。 |
|
|
|
| | 「ぼくが田中くんの人生を変えてしまって・・・悪いことをしたといつも思っていたんだ」
大学の恩師で、ぼくを事務所に紹介してくれた三浦先生があれから20年以上経った頃、東京で先生のライブを見に行ったときにそう言われたことがある。
「そんなことはないです」
ぼくはハッキリと先生に言った。
そう、あの時代がなければ今のぼくは間違いなくいない。
あの時代があったからこそ今、作家としてやっていけていると本当に思っている。
あれから何千本の劇画原作、ノンフィクション、フィクションを書き、何千枚の浜田剛史、タイソンといった世界戦のポスターをはじめとしてイラストを描いてきた。
週刊プレイボーイ、Nunnberなど雑誌のグラビアの写真も何千枚と撮ってきた。
そして気が付けば、劇画の原作本を中心に、ノンフィクション、エッセイ、共作としての本や海外での翻訳された劇画も含めると、2004年の4月23日に講談社から発売された「達摩」(画 所十三)の上下巻で丁度単行本も100冊目を出したことになる。
ここまでやってこれたのは「ぼくがミュージシャンだったような思い出」の時代があったからだ。 |
|
|