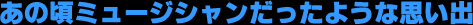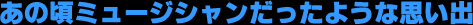| | 長い英五さんとのツアーが終わったとき・・・英五さんに映画主演の話しが舞い込んできた。
「映画の仕事をどう思う?」
英五さんがぼくに聞いてきた。
ぼくが狂のつく映画好きだと知っていて聞いてきたのだ。
とにかく映画はひと月に20本近くは必ず見ていた。
休み、ツアーの合間、仕事の合間、とにかく時間があれば、お金がなかったのでロードショーではなく、安い名画座の椅子に座っていた。
京都では京一会館、祇園座という毎週土曜日はオールナイトでやっている映画館があり、東京では文芸座、文芸地下が行きつけの映画館だった。
「映画、面白いんじゃないですか」
ぼくは英五さんに言った。
「じゃぁ、決めるか!」
英五さんはそう決心を声にすると、「撮影、見てみたいやろ」と悪戯っぽく笑みを見せて言ってきたのだ。
「み、見たいです」
ぼくも興奮ぎみに即答である。
英五さんとともに成城学園にある東宝撮影所へと小田急線に乗って向かう。
ぼくは映画の撮影期間中、付き添いという形で映画の撮影を見せてもらうことになったのだ。
タイトルは「トラブルマン 笑うと殺すゾ」、山下賢章監督の初監督作品である。
その山下賢章監督は、ぼくの大好きな岡本喜八監督の元で助監督をやっていた監督である。
ドキドキした。
あこがれの映画の世界という風景に圧倒されていた。
あのねのねに付いていたとき、TVのスタジオを見て興奮したことなど一度もなかったが、映画は自分の中の思いがまったく違った。
TV局の匂いと映画撮影所の匂いはぼくにとってまったく違うものだったのだ。
スタッフルームへ行くと、山下組の隣には当時話題の「影武者」の撮影に入っていた黒沢組の部屋があり、一度黒沢監督とすれ違い挨拶すると、「おはよう」と黒沢監督が言葉を返してくれた。
もうそれだけでぼくは舞い上がっていた。
「く、黒沢監督ですよ!」「市川昆監督ですよ!」「す、すげぇ!!」
ぼくが撮影所の中でひとつひとつのことに興奮する姿を見て、英五さんは笑っていた。
そして監督として初めて「スタート!」の声を発した山下賢章監督の合図とともに、河島英五初主演の映画の撮影が始まった。
|
|
|
|
| | 映画を創っている現場にぼくはいる。
そのことがぼくの気持ちを高揚させていく。
創造の塊と言われる映画を、プロはどうやって創っていくのか・・・
撮影前の衣装合わせ、本読みから見させてもらい、照明さん、美術さん、音響さん、そしてカメラ・・・そのときのカメラは後にぼくの大好きな岡本喜八監督の「近頃なぜかチャールストン」や「ジャズ大名」のカメラも担当した加藤雄大さんだった。
毎日のように創っていくという光景を目の当たりにできる。
プロの映画を創っているスタッフと映画の話しができる・・・
こんなしあわせなことはなかった。
「愛を乙うひと」「ラジヲの時間」「ひみつの花園」を後に制作する高井さんと映画の話しで盛り上がり、山下監督に監督の仕事が見たいというと、現場が終わると自宅マンションへ戻り、次の日の撮影のための脚本の直しまで「こうやって映画はできて
いくんだ」と、マンションまで同行を許され、ぼくにすべてを見せてくれた。
映画が好きだと言うと、それだけでこんなぼくにまで心を許してくれる。
映画に関わるものは皆、本当に映画が好きで、好きでたまらないといった気持ちが伝わってくる。
いつのまにか英五さんとは撮影所で別れ、ぼくは監督のマンションに泊まり込みで映画を創るというものを見せてもらうようになっていた。
毎日、朝から撮影を行い、終われば朝まで机に向かっている監督の姿・・・睡眠時間など2〜3時間の仮眠だけだ。
だがその姿にぼくは憧れた。
ものを創るためだけに夢中に生きている創作者の姿に、ぼくは憧れていた。 |
|
|
|
| | 撮影所でスタッフの人たちと話していたらひとりの俳優さんが入ってきた。
“トラブルマン”に出演するためにやってきた田中邦衛さんだった。
田中邦衛さんは「元気!」「元気!」と、すべてのスタッフひとりひとりに声をかけていく。
スタッフのみんなも「邦衛さん元気!?」と笑いながらの挨拶だ。
それだけで田中邦衛さんの人柄が見えてくる。
そしてスタジオの隅に立つぼくを見つけると、「あれっ?だれだったっけ?」と、いつも画面で見るあの笑顔で近づいてきた。
「河島英五についてきている田中です」
ぼくが答えると、田中邦衛さんは「同じ田中かぁ、よろしくなっ」と手を差し出し握手だ。
万弁の笑み。
一瞬にして田中邦衛さんという俳優が大好きになってしまった。
スターだというのに、まったく気取りや壁を造ることなく、逆にスタッフを大事にする、その気遣いにやさしさが見えてくる。
後に物書きとなって出会った高倉健さんもそうだった。
ラスベガスでボクシングのスーパーファイトを見た後、空港の待合い席に高倉健さんは座っていた。
『た、高倉健だ・・・』と遠く見つめていると、高倉健さんの横にいた知り合いのカメラマンがぼくを見つけ、そしてぼくにいきなり「紹介するから」と手招きである。
すると高倉健さんは椅子に座り本を読んでいたにもかかわらず、立ち上がってぼくの前に立つ。
そしてかぶっていた野球帽を脱ぐと、「自分は高倉健というものです」と真っ直ぐに頭を下げてきたのだ。
これにはまいった。
だれでも知っている健さんだというのに、そんなスターのそぶりなど見せることなく、これ以上ないといった礼儀の挨拶である。
すごい人だと思った。
もう感動と尊敬と、そしてその態度から伝わってくるやさしさに、ぼくは震えながら「田中といいます」と、頭を下げ挨拶を返した。
「いい試合だったね」
高倉健さんの笑顔での言葉だ。
その高倉健さんのやさしい笑顔は今でもぼくの脳裏に焼き付いている。
だから今でも、好きな俳優と聞かれれば「高倉健と田中邦衛」と、ぼくは尊敬の念とともに答えている。 |
|
|
|
| | 財津一郎さんがいた。由利徹さんがいた。金子信雄さん、河原崎長一郎さん、小松方正さん、多々良純さん・・・少し、「私は女優よ!」の多岐川裕美さんがいた。
ぼくが大好きだった山本晋也監督の痴漢シリーズの顔だった、久保新二さんもいた。
そんな中で、映画初主演の英五さんは浮いていた。
ベテランスタッフたちは役者ではない英五さんと距離を置いている感がある。
そんなときだ。
「ライブをやるか!」
英五さんが言ってきたのだ。
その日の撮影が終わった後、スタッフ全員を集めてスタジオでライブをやるというのである。
スタッフで自分をよく知らない人たちにも自分を知ってもらいたい・・・
それが歌だった。
それをスタッフに伝えると、「じゃぁ、ステージを造ろう」「照明も決めるか」「いい音出してやるぜ」と、美術さん、照明さん、音響さんたちがステージを造り始めた。
ぼくらがいつも見ているステージでの仕掛けではない。
映画で使用する機材を使っての仕掛けがスタジオのステージに施されていく。
英五さん、スタッフそれぞれが互いをおどかしてやろうと工夫をこらす。
フラッシュライトで英五さんの登場である。
そしてライブ。
「いくぜ!」
英五さんが叫ぶ。
叫ぶように歌い、そしてバラードは話しかけるように歌っていく。
50人ほどのスタッフの前で、滝のように汗を流し歌っている。
いつしかベテランスタッフたちも聴き入り、そして立ち上がり踊り出している。
距離を置いていたベテランスタッフたちが「最高!」と、ステージの英五さんに握手を求め叫んでいる。
一体になった。
英五さんを中心に、映画のスタッフ全員との距離が消え、一体になった瞬間だった。
歌の力・・・いや、河島英五の伝えるという情熱の力に改めて「凄い!」と感嘆した瞬間でもあった。 |
|
|
|
| | 英五さんの映画の撮影の間に、ぼくもデビューに向けて動き始めていた。
「新譜ジャーナル」「ガッツ」「オリコン」などに自分の名が事務所の広告に何ヶ月も前から載り始めていた。
レコーディングも始まった。
デビューシングルはA面が「ゴルゴダの丘」B面が「子供ならもっと高い山に登りたがるはずさ」。両方とも英五さんの曲である。
音録りが始まる。
「ゴルゴダの丘」に関しては、チュダー王朝の教会音楽の中の「シナオンの賛歌」のような賛美歌的なイントロといったイメージがあったのだが、ぼくの意見はまったく受けいられなかった。
そして出来上がってきた曲には、2番の頭の歌詞が「曲が長すぎる」というだけで削られていた。
「ここの歌詞は必要」と言っても、「黙ってできてきた曲を歌え」それが答えだった。
アーチストとして意気込んでいた心が一瞬にして萎えていく。
そして自分の中に不満の残ったまま、東京のスタジオで歌入れも始まっていった。
そんな最中、事務所の主催する京都でのアマチュア音楽祭にいきなり出されることになった。
「賞は決まっているからミスはするな」
信じられない言葉がぼくの耳に入ってくる。
その音楽祭での賞はデビューに箔を付けるためだったのだ。 |
|
|