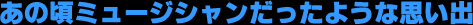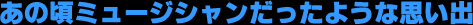| | 「それでプロでやっていくつもりか!」
リハを終えたぼくに向かって英五さんの怒りの声だ。
原因はわかっている。
声が出ていないのだ。
一年、ほとんど声も出さず、ギターも弾いてこなかったことでボロボロになっている。 泣きたい気持ちだった。
だがステージに立つ以上、そんなことが言い訳になるはずがないこともわかっている。 だから英五さんは、ぼくの一年の日々のことをわかっていて怒っているのだ。
そして、「よかったやないか、今からは毎日歌えるだろ!」と、怒りの声の最後にそう言ってくれた。
「今日から毎日歌える」・・・つまりは毎日がミュージシャンだ。
毎日がミュージシャン、つまりプロということとはどういうことか・・・
その答えを目の前で英五さんが見せてくれる。
ほとんど毎日がコンサートの日々。
コンサートが終わればその土地のスタッフと打ち上げだが、英五さんはお礼の挨拶をすると、ほとんど酒を飲むこともなく食事だけをしてホテルの部屋へと戻っていく。
明日のコンサートのために体調を崩さないためだった。
そして朝は必ずジョギングだ。
それは毎日のステージのための体力維持である。
ツアーの日々、ステージをつねに最高の状態で挑むために生きるといった毎日を英五さんは送っている。
そのためだけに生きる。
プロとはそういうものだと英五さんは生き方で見せてくる。
ぼくも朝のジョギングに参加して、英五さんを追いかけるように走り始めた。 |
|
|
|
| | 1ベルが鳴る。
ぼくは楽屋から出てステージへと向かう。
当時のステージには客席との間に緞帳があり、その緞帳の向こうの客席から観客のざわめきが聞こえてきている。
そのざわめきを耳にしながら薄暗いステージで最後のギターのチューニング確認だ。
そして2ベル。
観客席の照明が落とされるとともにざわめきが消えていく。
緞帳の向こうから観客たちの期待と緊張の空気が静寂とともに押し寄せてくる。
ギターを抱えたぼくの足は震え、最高の緊張が身体を縛る。
ステージ横で合図を待っているマネージャーのIさんに向かって、ぼくは緊張の顔で頷ずく。
その瞬間、本ベルが会場に鳴り響く。
本ベルが鳴り終わると同時にぼくは覚悟を決めるといった思いでギターをかき鳴らす。
緞帳が静かに上に向かって開くとともに、目の前にいくつもの顔とそして拍手だ。
次ぎの瞬間・・・
バッ!
緞帳が顔の位置を通り過ぎた瞬間(とき)目の前からすべての光景が消える。
まるで真夏の太陽だけの光の世界、目にピンスポットが突き刺さったのだ。
その眩しすぎる光の世界が合図となり、身体から緊張は消え熱い塊が沸き上がる。
声だ!
観客に向かっての声が身体から弾けたように飛び出していく高揚感。
30分から40分の短いステージ・・・
そんなステージの光の中で、ぼくは声を張り上げることの陶然の快感をぼくは知った。
その快感が毎日のように訪れるツアーはまだ始まったばかりだった。 |
|
|
|
| | 「どさまわり」という英五さんが創った曲がある。
あのねのねが「青春旅情」という名でシングルで出した曲である。
その曲を英五さんと旅(ツアー)の合間によく唄った。
全国を旅していると、田舎の駅で乗り換えに1時間以上待つなどということなどよくあることだった。
そんなときは英五さんとギターを取り出し、電車の来ないホームに座って歌を唄いだす。
最後は必ずマネージャーのIさん、照明のOさんも加わって「どさまわり」を声を張り上げ唄っている。
汽車にゆられ〜一日のいくらかを〜
過ごす毎日が続いています〜
北から南へ〜東へ西へ〜
あちこちの人と人との〜
心と心を〜つなぐ架け橋に〜
なれたらいいと思います〜
雨の日も〜風の日も〜
揺れる汽車の中で〜
思い出と〜見知らぬ夢との〜
間を行ったり来たり〜
今でもこの唄をくちずさむと、あのときの季節の風が吹き、土地の臭いが包み、そして抜けるように蒼かった大きな空が目の前に広がってくる。 |
|
|
|
| | ツアーに出て、ホールとホテルしか知らないというミュージシャンたちの話しをよく聞く。
たしかにぼくも、「あのねのね」に付いていたときのツアーは、ホテルとホールだけの記憶しかない。
だが、英五さんとのツアーは、その街、その街を踏みしめたツアーだった。
昼の3時にホールへ入るという約束で、英五さんたちとは別行動で早朝にホテルを出て、次ぎの街へとひとりで移動したことも何度もある。
せっかく知らない街に来ているというのに、その街の空気を知らないで去るなんて寂しすぎると思ったからだ。
とにかく街を歩いてみる。
海の街だったら海へ向かい、山に囲まれた街だったら少し山を登ってみる。
ぼくが少年時代育ったのは広島と四国の丸亀という街だ。
だからだろう、海の匂いと木々の匂いをかぐと知らない街でも懐かしい風がぼくの身体を吹きぬけていく。
また、城下町であれば城を見に行き、名産があれば食べ歩く。
そしてステージでその日見つけた街の話しをする。
するとぼくと観客の距離は一瞬にして縮まっていく。
楽しかった。
ステージが楽しかった。
歌うことが楽しかった。
ぼくが本当にミュージシャンだったと言えた短い瞬間(とき)だった。 |
|
|
|
| | ツアーの合間の今も思い出す風景がいくつかある。
天草でコンサートをやり、その夜地元のスタッフに連れられて海へ行った。
そこにはいくつもの流れ星が潮の音とともに闇に消えていく光芒があった。
沖縄では同じ事務所のミュージシャン、あらい舞ちゃんもやってきて、後に英五さんのバックを手伝うこととなる、沖縄の伝説のハードロックバンド「メデューサ」の喜屋武幸雄氏とマリーに連れられてコザ、そして金武で、米兵のマリーンの連中を前に歌い、朝までハードロックに騒いだ思い出がある。
それから何年経ったころだろうか・・・
ぼくが頻繁に沖縄へ行くようになったころ、メデューサでドラムを叩いていたコーちゃんと、コザで偶然の再会があった。
当時コーちゃんのいたオキナワというバンドには、やはり伝説のバンド、「紫」のジョージ、チビ(宮永英一)などがいて、そこにコンディション・グリーンのかっちゃんも加わり、会えばとにかくみんなでよく飲んだ。
そして最近、オキナワ音楽つながりでまた出会いがあった。
オキナワのミュージシャン、ローリーさんのライブの打ち上げで、ぼくの隣に座ったのが、今やスーパーバンド、モンパチ(MONGOL800)のプロデューサー、浜里稔氏で、浜里氏は何と昔ぼくのいた事務所でアルバイトをやっていたということだ。
浜里氏からは懐かしい名前がいくつも飛び出してきた。
世の中とはまったく狭いものである。
(左の写真、嘉手納基地の中、喜屋武幸雄、マリー、娘のアリス、舞ちゃんと。シャッターを切ったのは英五さん) |
|
|