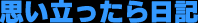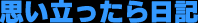| | 2011年1月19日
プールに飛び込み目を閉じる。
ドルフィンキック。
いつもそうして泳ぎ始める。
そこはプールではなく、海をイメージする。
御蔵島。
イルカたちの声を追いかけ深海へとドルフィンキック。
青が深くなる。
空の青が宇宙に近づくにつれ青くなるのと同じ。
海も宇宙へと繋がっている。
宇宙をイメージすると、何かのスイッチが入るのか、言葉が降りてくる。
「Only one」
ぼくはよく、あなたにとっての「Only one」は何かと人に聞く。
人はだれも「Only one」であることはわかっていてぼくは聞く。
聞いているのは、「Only one」の「存在」になれるかどうかということだ。
その存在が「プロ」になることだとぼくは思っている。
そんなことを考え宇宙を感じながら泳ぎ続ける。
自分の「Only one」としての「存在」。
それは、「縁」が育ててくれたとわかっている。
ぼくを「Only one」にしてくれた何人もの出会いという「縁」。
20代のころ、まだ本当にお金のなかったころ、ぼくは「Only one」に、その「存在」になろうとしていた時期。
ボクシングの世界にリアルに入り込み、これだけのことは、描くことではだれにも負けないと自負していた時期。
ラスベガスで、マービン・ハグラーVSトミー・ハーンズという世紀のビッグマッチがあった。
今では、まさに伝説となっているボクシングのファイト。
その試合にどうしても行きたかったが、お金がなかった。
当時、1ドルが250円だった時代。
その試合を見に行くには、50万円はかかる。
そんなとき、美味しんぼの原作者である、雁屋哲さんが言った言葉。
「お金で夢を摘み取ってしまうのか!?」
雁屋さんは黙ってぼくに50万円を渡してくれた。
「本当にやりたいなら、お金じゃない。お金は返せばすむこと、やりたいことはその瞬間にしかないからな」
そのときのアメリカ・ラスベガスがぼくにとって、「Only one」の「存在」にしてくれた旅となった。
そういうことなんだ。
あのとき雁屋さんがいなかったら、今の自分はあっただろうか?
そういうことなんだ。
ぼくはその後、大きな借金をすることにもなるが、その借金は今、ちゃんと「Only one」の存在にしてくれている。
プールの中で目を閉じる。
青が深くなり宇宙となる。
この青の世界の中で、ぼくは「Only one」の存在ですか!? |
|
|
| | 2011年1月15日
水のように生きたいと思っている。
道教の思想を組んだブルース・リーの大好きな言葉。
心を空にしなさい。水のように、形態や形をなくしなさい。
水をカップに入れると、カップになる。
水をボトルに入れると、ボトルになる。
水をティーポットに入れると、ティーポットになる。
水は流れることができ、激突することもできる。
水になりなさい。わが友よ。
この言葉を知ったのはいつだっただろうか…
20代だったような、30代だったような。
もしかしたらこの言葉を知る前から、そう子供の頃から「感じていた」言葉。
形などいらない。
自由というものは、形のないこと。
形がないということは、何からも縛られないということ。
そして何にでもなれるということ。
水のように流れ、日本を、世界を旅しつづけた日々。
その日々で出会った何千もの感動。
ずっとずっと昔から水のように生きたいと感じていたのかもしれない。
少し本気で考えている。
海と森と川のある、身体が自然と一体になれる場所に仕事場を移したいと考えている。
自然のエネルギーの中で生きる。
そこで創造を生む。
具体的に思う場所もある。
だが、そこはひとつの拠点。
形には収まらない。
ブルース・リーはぼくに言う。
流れる水は決して腐敗しない。だから「流れ続けなさい」 。 |
|
|
| | 2011年1月12日
冬のプールでクロール。
この時期になると、プールには人はほとんどいない。
静かに、一定のリズムを刻みながら水と一体になるように泳ぎ続ける。
泳ぎながら考える。
ひとりの若いアーチストの友が投げかけてきた言葉。
「自分が満足して幸せに向かう道が、思うままに生きる道なら、自分を通すほどに誰かを傷つけることがある」
友の言葉を自分に置き換えて考える。
自分が生きる道。
ずっと思うがままに生きてきたというか…やりたいことを形にするためには、そのためだけに生きることで、周りに淋しい思いをさせたり、傷ついけたこともたしかだ。
でもね。
勝ち取ればまたそれが変わってくるよ。
北野武がずいぶん前だけど、「オレは勝ち取ったから好きなものが創れる」って言ったことがあるんだ。
そのとおりだとぼくは思う。
たとえば、30代の頃は、10年間、実家に一度も帰ってないんだ。
世界中、日本中旅ばかりしていて、実家の近くだって何度も通っていたというのに…
親にまったく連絡もしない親不孝。
でもね、そのころ、マンガや、ノンフィクション、エッセイ、コラムといった週刊、各週、月刊と連載を持っていたことで、親がこう言ってくれてね。
「毎週、毎月いっぱい手紙をもらっているから大丈夫だよ」
冬のクロールで、友の言葉で、大事な宝の言葉を思い出した。
(今回、画像なしです。) |
|
|
| | 2011年1月5日
映画「あしたのジョー」の試写に行ってきたよ。
これは違うだろといった、リアル面など突っ込み所はいくつかあったが、映画を見ながら、自分にとって「あしたのジョー」がいかに大きな作品だったか、それを思い知らされたんだ。
そう、たまらんのだよ。
「あしたのジョー」というだけでたまらんのだよ。
なぜだか泣きそうになってしまうのだよね。
ジョーがいて、力石がいて、段平がいるだけで泣きそうになってしまうんだよね。
1968年、ぼくが11歳のときに「あしたのジョー」は週刊少年マガジンで始まったわけだが、あのとき、「あしたのジョーを読むために生きた」それほどの思いで読んでいたんだって、思い返せばそういうことだったんだ。
そう、自分の歩む道すべてが、「あしたのジョー」で決まったと、ここまで生きていて確信できるもんな。
ジョーを探すことから現実のボクシングにのめり込み、描きたいと追いかけたボクサーが世界チャンピオンになり、いつしかマンガだけではなく、専門誌、スポーツ雑誌でまでボクシングを書く、そして撮るまでになっていったんだ。
すべてあしたのジョーを追いかけたことからできていった道。
ボクシングだけじゃなく、描いてきた、創ってきたすべてがここから続いた道だったと間違いなく言えるよ。
今もね、ジョーを語るだけで、もう、胸が張り裂けそうになるまで、もう息が苦しくなるまでの思いが込み上げてくるんだ。
本当にたまらんのだよ。
目の前に実写のドヤ街があり、そこにジョーが立っているだけで本当にたまらんのだよ。
その世界を描いたちばてつや先生と、今、大学でいっしょに居られること、先生と夜、こっそりギターとウクレレでバンド練習をしていること…
大学への行き、帰り、車の中で何十回と語り合っていること…
自分が生きてきた道を振り返れば奇跡としか思えない状況だろ。
12年前に出した、ひたすらボクサーたちを追いかけ書いたフォトノンフィクションの単行本「拳雄たちの戦場」の、その冒頭で、ちば先生が書いてくれた言葉があってね。
その言葉の最後にこんな言葉を書いてくれたんだ。
「この一冊のさわりだけでも読んでいたら…「あしたのジョー」も、もっとさらに豊富なキャラクターに彩られもっと深みのある、もっと人間味に溢れた作品になったのではないか…と、今更ながらであるが残念でならない」
許されないよね。
許されないけど、こんな嬉しい言葉はないよね。
自筆の原稿を手にしたとき、身体が震え、自分の中の魂までが吼えたんだ。
あぁ、すげえよ。
映画を見ながら、別に泣けるシーンでもないのに、涙が流れてしまったよ。
ちば先生に、映画を見て忌憚のない感想を言ってくれと言われているけど…
「あしたのジョー」という、とてつもなく大きな作品と出会った奇跡。
映画を見ながらも、ただその奇跡の大きさを、「あしたのジョー」の凄さを、ただただ思い知らされた、それが今回のすべての感想です。先生。 |
|
|
| | 2011年1月3日
あけましておめでとうございます。
少し遅れた挨拶はさておき、ここ毎年、初詣は江ノ島と決めている。
なぜかと言われると、この場所でなければというある思いがある。
自分の作品でも、「剛球少女」「ウェーブのいた夏」など、この場所を舞台としたものがいくつかある。
それだけ何度もこの場所へは通っているし、思い入れだって江ノ島を中心としてこの湘南に歩んできた時代の数だけ人、店、場所とある。
この場所に来だしたのは18のときだから、1975年ということになる。
一番最初に来たのは、10年前に亡くなったぼくの人生最初の師匠である、あすなひろし先生が葉山に引っ越してきたときだった。
そう、あのとき、どうしても江ノ島を見たくて、先生の家に行った帰りに、江ノ島へやってきたのだ。
なぜ、あのとき江ノ島に拘ったのか…
ぼくはこの江ノ島が好きだが、みんなが持っているサザン的なイメージとは少し違う。
この場所は鬱屈した、胸が掻きむしられるほどの、そして呼吸する息が苦しくなるほどの、ドロリとした重い苦しさの青春というイメージだ。
そのイメージに惹かれてこの場所に来たのが最初だった。
そのイメージをぼくに植え付けた作品がある。
「八月の濡れた砂」
1971年の夏に公開された、藤田敏八監督の名作である。
当時中学生だったぼくは、この映画を隠れて見に行き、テレサ野田の美しさとともに、広瀬昌助、村野武範の演じる少年の、鬱屈した、胸が張り裂けそうで、この思いをどう発散したらいいのか。
セックスと自由と、そしてまだ何者でもない、力と言えばただ暴れるだけの力しかない二人の少年、特に広瀬昌助演じる西本清が中学生のぼくにとって、魅力…いや違う、ドロリとしか表現できないのだが、心の中にそのドロリが西本清というキャラを通して強烈に入ってきたのだ。
今まで感じたことのない苦しいほどのドロリ。
それがあの映画の舞台、江ノ島と重なった。
石川セリの歌う「八月の濡れた砂」とともに、そのイメージが重なった。
最初に江ノ島へ来たときは、真夏の熱い日だった。
目が開けないほど眩しい陽射しの中で、欲望が掻きむしられる光景はたしかにあった。
ドロリだ。
ビキニの女性が卑猥に見える…田舎の海水浴場では決して感じない、「八月の濡れた砂」のドロリがここにはたしかにあった。
それからすぐに、沖縄でも同じドロリを感じることになる。
ベトナムへ向かうマリンの連中から感じた、もっと強烈なドロリ。
それが人間の持つ欲望の臭いに近いと感じ始めたのはそれからずいぶん経ってからである。
今の江ノ島には、あの時代のような欲望のドロリは無くなってしまったが、ぼくは時々、そのドロリを思い出すために江ノ島に向かう。
つまりは自分の原点の、欲望を、夢を、力を、それをどうすれば手に入れられるのか、発散できるのか、それがわからず叫び声を「うぉんうぉん!」と上げていた、あのときの自分を思い出すためだ。
江ノ島で感じていたドロリ。
あのエネルギーは半端なものではなかった。
年齢を重ねてわかることがある。
「八月の濡れた砂の中」でもそれは表現されている。
大人という常識に縛られた人間に、その常識に縛られてたまるかと、叫びつづける大人になりたくない人間がいる。
ドロリは、欲望とともに縛られたくなくて喘ぐ心の藻掻きだ。
常識って何なのだろうか…
この歳になっても、「常識に縛られてなるものか!」と、毎年、年の初めに、この場所から初めるために、ドロリを忘れないためにここへぼくは来ているような気がする。
そう、あのころの「あしたのジョー」の心を忘れないためにだ。 |
|
|