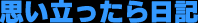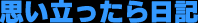| | 2004年12月27日
横浜アリーナで行われたサザンオールスターズの年越しライブ、「暮れのサナカ」の初日に行ってきた。
プラチナと言われるサザンのチケット、取れたのはセンターのど真ん中の27列目という、ステージ全体が目の前のちょうどいい位置で見渡せる最高の席である。(チケットを取ってくれたカミさんに感謝)
ライブが始まると、込み上がってくるものがあった。
音楽とは自分の生きてきた道での流れていた風である。
だから曲を聞けば、その曲を聞いていた時代の風景が蜃気楼のように目の前に広がり、思い出がリズムの鼓動とともに蘇ってくる。
サザンを初めて聞いたのは21歳のときだった。
まだぼくがミュージシャンをやっていた時代である。
そうだ、東京からやってきた学生バンドが面白いライブをやっていると、京都の「拾得」というライブハウスで初めてサザンの名を聞いたことを思い出した。
それからすぐに「勝手にシンドバット」でサザンはメジャーとなり、「いとしのエリー」を聞いているときにぼくはミュージシャンを辞め東京へと出て行っのだ。
サザンの曲を聞きながら海に向かって車を飛ばしたことなど数え切れないほどある。
今まで乗り換えてきた何台もの車に染みこんだ思い出があり、そのすべてにサザンが風として染みこんでいるわけだ。
物書きになって、「剛球少女」「ウェーブのいた夏」など、湘南を舞台にしたいくつもの作品を書いた。
書きながらいつのまにかサザンの曲を口ずさんでいたことも何度もあった。
ステージから桑田佳祐が叫んでいる。
「みんなエネルギーをくれてありがとう!」
ぼくは叫んでいる。
「ぼくらこそいっぱいのエネルギーを、サザンありがとう!」
今でもサザンは聞いている。
懐かしいではなく、その時代の曲として今でもサザンの曲を風のように聞いている。
だからぼくの生きた道にはいつもサザンの曲が風となっていた。
甘酸っぱい思い出、藻掻いていた青春、感動に涙した風景・・・
みんなサザンの曲で風が吹く。
今日のライブで流れてくる曲はみんな知っていた。
そのことに、生きてきた時代とともに心に染みこんでいるサザンの曲の凄さを思い知る。
自然に身体が動き、自然に曲を口ずさんでいる。
汗だくになっていた。
客席でいつのまにか汗だくで、風の中で踊り歌っていた。
感動で吹き抜けた2時間半のライブ。
ぼくの中でサザンの存在が今日またひとつ大きくなった。
そして気付けば、サザンの新曲、「愛と欲望の日々」の振り付けまで、ぼくは踊れるようになって横浜アリーナを出てきていた。 |
|
|
|
| | 2004年12月8日
フォークシンガー、三浦久の「吉祥寺マンダラ2」で行われた、毎年恒例の年末ライブに行ってきた。
三浦久はぼくの大学のときからの恩師である。
だけど今回は、三浦先生ではなく、フォークシンガー三浦久のライブを感じてきたと今日は書きたい。
フォークシンガーこそが自分の望んだ生き方と、三浦久が大学教授を辞めてもう何年たつのだろうか・・・
そんなことを考えながらぼくは三浦久の歌を聞いていた。
ぼくが出会った18歳のころに聞いた歌が流れ、そして三浦久の最高の名作といっていい新曲、「千の風」へと繋がっていく。
風を感じていた。
そうだ・・・三浦久の歌には風の歌が多い。
紙飛行機を風に乗せて飛ばしたかった子供のころの歌から、風のような生き方をした「山頭火」を歌い、「宝福寺にて」では京都の風が流れてくる。
そして三浦久が母と過ごした辰野から、その母の死が書かせてくれたという風の歌、「千の風」へと繋がっている。
ステージではサポートの関島岳郎さんが、三浦久の風を受けるようにリコーダー、そしてチューバの、そう、吹くのではなく風を吹きこんでいっている。
静かに流れる風もあれば、太く舞う風もある。
だがそれが優しい。
風が流れる。
それは辰野の風であったり、京都の風であったり・・・
三浦久の生きてきた風がライブハウスに流れている。
本当にすばらしいライブだった。 |
|
|
|
| | 2004年12月7日
英五さん、今日大阪産経新聞の記者の方が、「河島英五さんの話しを聞かせてほしい」と、大阪からぼくのアトリエのある東京の鷺ノ宮まで訊ねてこられました。
産経新聞紙上で連載している、「凛として」という人物伝で、来年の1月に5回に渡って英五さんを取り上げたいということでの取材です。
英五さんについてぼくの話せるのは、75年から79年までの4年でしかありません。
ちょうど英五さんのメジャーデビュー前から、「酒と泪と男と女」のヒット、そしてペルーの旅を終えたあたりまで・・・ぼくが近くで英五さんを見続けた日々です。
面白いもので取材で話しているうちにいろんなことを思い出しました。
英五さんと出会ったころは怖くて、いつもそばにいながら口を聞くことができなかったって、今、英五さんが聞いたら「何言うてるねん」と笑われそうですけど、ホントです。
あのころ英五さんはいつも怒っていて、ギラギラしていて、エネルギーの塊のようで、触れるとそのエネルギーが爆発してしまいそうで、一言会話をするのにホント勇気と覚悟がいったものです。
でも今になってあのころの英五さんが何に怒っていたかわかるような気がします。
飢え。
「何かいいことないかな」と大声で叫び、「てんびんばかり」では自分の内に向かって叫んでいた・・・叫ばずにいられなかった飢え。
妥協しない、あきらめないからこそ心を雑巾のように最後の一滴まで絞るようにして歌を生み出し、それは藻掻きながら飢えた叫びの歌だったのだと・・・
そしてそれをわかってくれない時代への怒り。
とにかくその飢えの大きさにぼくはいつも圧倒されていました。
だから響いてきていたのです。
あのころの英五さんの歌が、言葉が、仕草が、生きているすべてがぼくには響いてました。
とことん真っ直ぐに生きる姿。
自分に正直に真っ直ぐ生きるということが、社会で生きる中でいかに困難なことだったか・・・
真っ直ぐに生きようとしたら、英五さんが創った「子供ならもっと高い山に登りたがるはずさ」の歌詞にあるように、「あっちでゴツン、こっちでゴツン・・・」って、ぶつかりの連続で、だからみんなはぶつかり合わない、やさしさという妥協の生き方を選んで、それを大人になったとごまかして・・・
でも英五さんはそんな妥協の生き方は、自分の辞書にはないって生き方でしたよね。
その生き方から発するエネルギーのあまりの凄さに、ぼくは息ができないくらいの響きを、魂を感じていたということです。
その響いていた魂の話しを思い出し、そして今日、記者の方に話してきたというわけです。
取材を終え、アトリエに帰り、机の前に座っても、まだまだいろんな英五さんとの日々の魂の響きが湧くように思い出されてきました。
そしてあらためて思っています。
たった4年の間でしたが、ぼくが生きてきている中での英五さんから受けたことの大きさです。
明日はぼくの尊敬する、英五さんも大好きだったジョン・レノンの命日です。
その命日に、英五さんが顔がレノンみたいだって言いながら、ぼくの前で似顔絵を描いてみせた三浦久先生が東京の吉祥寺でライブを行います。
もちろんぼくは行ってきます。
それと来年2月にぼくも48歳になってしまいます。
もう英五さんと会えなくなってしまったときの、英五さんと同じ歳にぼくもなってしまいます。 |
|
|
|
| | 2004年11月29日
「冬のソナタ」がブームを起こしてからの韓流には驚いている。
ぼくが韓国へ頻繁に行っていたのが87年、88年である。
ソウルオリンピックによって、韓国が凄まじい勢いで生まれ変わっていた時代だ。
実はその時代からぼくは韓国映画の密かなファンである。
イ・ドゥヨン監督の「桑の葉」、ペ・ヨンギュン監督の「達磨はなぜ東に行ったか」など見ていた80年代。
そしてぼくが本当に韓国映画に夢中になったのが、ホ・ジノ監督の「八月のクリスマス」で泣かされてからである。
それ以降、自分の持つエッセイページでも「今、韓国映画が熱い!」などと書いてきたわけだが、ついに99年のカン・ジェギュ監督の「シュリ」が日本でも大ヒット。
2000年にはぼくが一番の名作と思っているパク・チャヌク監督の「JSA」が公開され、そして2003年からは信じられないほどの韓流が日本で起こっているというわけだ。
つまりぼくは、韓流の流れで韓国映画を見出したのではなく、80年後半から韓国映画はリアルタイムでずっと見てきた韓国映画ファンだと自負している。
そして今回見に行ってきたのがクァク・ジェヨン監督の「ぼくの彼女を紹介します」だ。クァク・ジョヨン監督は、今ぼくが一番好きな監督で、「猟奇的な彼女」「ラブストーリー」など、とにかく見に行くごとに感動させられている。
そして今回、「猟奇的な彼女」のチョン・ジヒョンを主演に、「火山高」で強烈なキャラを見せてくれたチャン・ヒョクを向かえての作品となれば、もう公開まで待てずに今日、試写会に行って来たというわけである。
いきなり参った。
冒頭でボブ・ディランのKnockin` on Heaven`s Doorの曲が流れてくる。
青春である。
ぼくの青春の曲で、もう一気にラブストーリーモードに突入。
話しとしては、少し突拍子もない話しなのだが、「猟奇的」と同様、チョン・ジヒョンのキャラに引っ張られ、大いに笑い、そして泣かされてしまった。
試写会が終わり、外へ出ると風だ。
冷たい、冬を感じる風が吹き抜けたが、その風を心地よく身体で受け止める。
映画の中でのキーワード、「風」にとにかく泣かせてくれたものだから、ぼくもその気になって風を感じたというわけだ。
映画は12月11日から公開だそうだが、ぼくはもう一度「僕の彼女を紹介します」を見に行くことにする。 |
|
|
|
| | 2004年11月26日
昨日はわが草野球チーム「バッカス」の優勝祝勝会。
11月4日の日記にも書いたが、まさにミラクルな優勝だったこともあり、今年のシーズンを振り返って、飲んで、食って、騒いで・・・本当に最高の野球仲間たちだ。
そしてキャプテン岡田さんから渡された今シーズンのぼくの成績表。
打率は280ながら、出塁率は419。投手成績も4勝2敗と、自分としても「よくがんばったじゃん」の納得の成績だった。
それにしても岡田さん、毎年全試合の戦績、そして今年は対戦チーム別戦績表までと感謝のひとことです。
そして藤井さん、優勝記念の写真ありがとうございました。
そして今日はS出版社での打ち合わせを前に、少し早くアトリエを出て、渋谷で「ロード88」という邦画を見てきた。
白血病に冒されたひとりの少女が、スケボーで四国一周のお遍路88カ所巡りの旅に出る話だ。
ぼくは四国に住んでいたことがあり、また16歳の高校の夏、自転車で四国一周をし、88カ所の中のいくつかの寺も巡ってきたこともあって、そんな懐かしい風景を楽しみたいといった感覚で入った映画だったが、これが面白かった。
旅は出会いと成長といった、ストレートな話しなのだが、そのストレート結えの感動だった。
そんな感動の余韻とともに神保町のS出版社で打ち合わせをし、またバッタリと、少年ジャンプでの連載を始め、数々の作品をいっしょに創ってきた担当編集というより、もう25年来の友人である松井氏とロビーで出会い、もうすぐやはり知り合いの、カメラマンの四宮さんも来るというのでメシでもという話しとなった。
S出版社の隣りの大手S出版社の編集長というより、やはり友人の荒木氏も呼んでのメシとなったわけだが、同年代のぼくらが集まればいつものことながら創造の話しだ。
「こんどあれを創ろう!」「これをやろう!」
とにかく熱い。
その場の話しだけじゃない。
こうやって話しながらいくつもの作品をぼくらは創ってきた。
メシだけの予定が、それぞれまだ仕事があるというのに、ギリギリまで飲みながら創造の話しである。
エネルギーがわき上がってくる。
創りたいと心に秘めたものが形をなしてくる。
ふと、高校のとき自転車で四国一周を走ろうとペダルを漕いだ一蹴の瞬間を思い出した。
まだ見ぬ未来へのワクワクする思いの一蹴。
この歳になっても16歳の夏の一蹴ができていることが嬉しい。 |
|
|