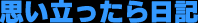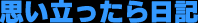| | 2012年6月30日
そうだったな…と思う。
生きてきたことを思う感情が身体から漏れてくる。
6月23日、大学の恩師、三浦久先生のライブハウス、長野の辰野にある「オーリアット」でのライブで“あのねのね”の二人に会った。
清水国明さんとは10数年ぶり、原田伸郎さんとは30年以上ぶりだった。
ぼくが、18歳のとき三浦先生に紹介され入った京都の音楽事務所に、“あのねのね”は所属していたのだ。
当時、日本中のだれもが知っている、大スターで、ボク自身も高校のころの「あのねのねのオールナイトニッポン」は必ず聞いて、ラジオの前で笑い転げていた。
そんな、それまでTVや、ラジオの中でしか見たこと、聞いたことのないふたりと事務所で出会ったのだ。
他にも、その後やはり大スターになっていく、河島英五さん、尾崎亜美さんや、やしきたかじんさん、笑福亭鶴瓶さんなどがいた。
当時ぼくは、マンガで賞をもらい、現在は集英社の取締役になっているT編集が、当時の担当編集になっていたわけで、言ってみればそのまま音楽ではなく、マンガをやっていればプロとしてすぐにデビューできていたと思う。
だが、当時、ぼくは音楽の道を選び進んでいくことになる。
それはきっと、ものを創るというためには、このままでは経験不足だということが、デビューしたとしても、マンガ家で生きていくための根底ができていないことが本能でわかっていたのだと思う。
当時、自転車で時間さえできれば「知りたい本能」で日本中を旅していたのだが、その旅と同じ「知りたい本能」が働き、プロ意識のないまま音楽事務所に入っていったと、今思えば、そういうことだったように思えている。
ぼくは、事務所に入って、あのねのねの二人とは、一年間いっしょに行動することになる。
事務所の社長の考えで、東京のテレビ・ラジオで何本もレギラーを持っていたふたりに付いて、つまりは芸能界で「顔」を売るという戦略からあのねのねのふたりに付けられたのだ。
その後、河島英五さんと全国83カ所をツアーで廻ったときのことは、HPの「あの頃ミュージシャンだったような想い出」で書いているのだが、自分の人生にとってとてつもなく大きな毎日だったと、人生を決めた毎日だったとまで書いている。
それに対して、あのねのねといた一年は、ただ忙しいだけの、疲れただけで、心のどこかで「無駄」を感じていた一年だと書いている。
だが違う。
年齢を重ねるごとに、あの一年の大きさがいかにおおきかったか見えてきたのだ。
芸能界という言葉は大嫌いだった。
その言葉の、ぼくの中の根底にある芸能界という世界は、きっとぼくはその空気が苦しかったのだと思うが、虚栄や、矜持、搾取や懐疑など、世に出るための、また自分の地位を守るためのドロドロしたものが渦巻いていた…そんな苦しさがいつも溢れていたのだ。
番組内、番組の外でも、生き抜くためのアピールする必死のタレントさんたちの姿を目にする。当時、それは「いやらしく」感じていたし、「アーチストなら実力で勝負しろ」などと蒼い思い考えでしか見ていなかった。
だれもが実力で勝負したいのだが、それ以上にチャンスががないのだ。
いくら実力があっても、見てもらえることができなければ「無駄」でしかない。
チャンスとは実力を見てもらう唯一の瞬間。
そのためだったらいくらでも卑屈になれる…
たとえば、あのねのねがレギラーだった「うわさのチャンネル」などでは、チャンスをもらった新人のタレントなど、大げさに言えば、その一瞬にすべてのエネルギーを出し、それでうけなかったら死ぬといった覚悟をヒシヒシと感じてくる。
本当に死ぬ気でカメラの前に立つ顔というのは、こういうことなのか…
プロとは、こういう覚悟を持ったものとの闘いなのか。
後にスポーツを取材するとき、いくつもの「死」を覚悟した選手の顔と出会うのだが、まさに、それを18歳のときプロの覚悟を感じることができていたということだ。
ピンクレディーが始めて舞台に立つ前の楽屋の廊下、舞台袖でふりつけを、まだ出番でもないのに滝のような汗を流しながら合わせている姿(もちろん「死」を覚悟したものがそこにもあった)…これが売れていくはじまりのエネルギーだったのだと、そういう姿も見ることができてきた。
一度、大阪の番組に向かう飛行機で、となりに山口百恵さんが座ったことがある。
少し話しをしてくれたのだが、後に物書きになってから高倉健さんとラスベガスでお会いする機会があり、それと同等の、声、表情、しぐさ、それだけで、これは感動以上の、存在、生命力すべてが包み込む震え…きっとそれがオーラというものかもしれない。
存在がプロとなっているエネルギーだ。
つまり、あの一年、とてつもなく忙しいことばかりで、何をやっていたのか記憶が薄いのだが、その反面、あのねのねといることで、あのTVの時代に、TVにあらゆる大きなエネルギーが集まってきている時代に、だからこそ時代のエネルギーを感じることができ、「生きるための力」を「知った」一年だったと思っている。
ライブが終わり、まるで30年以上もタイムスリップしたように、あのねのねとの想い出話しはつきなかった。それとともに、時間はそれぞれが生きてきた感情で話し合えることができるようになってきていた。
たとえば3.11。
あのねのねも同じで、ぼくとは違う場所で、だが同じ思いで今も動いている。
たった一年だが、同じ空間で生きたものは、どこか同じ思いがあるのかもしれない…いや、生きてきた中で、同じ事務所だったも含め、あの出会いがあっての同じ思いになってきたのだ。
そう、河島英五が阪神淡路大震災でどれほど動いたか、ぼくらは仲間として見てきた。
あのねのねも、ぼくもそれは知っている。
河島英五は今はいないが、その思いは生きてると…だから。
清水さんがつぶやいた。
「英五が生きてたらなぁ」
その言葉に、あの時代、同じ時代の風の中で生きてきた、原田さん、ギターリストのノーマン、そして、あのねのね・ぼくにとっての恩師三浦久先生は、きっと同じことを考えていたのだと思う。 |
|
|
| | 2012年5月27日
いつもカメラを持っている。
10代のときからだ。
仕事場の資料部屋には何万枚のネガとポジフイルムがある。
そのフイルムを時間のあるときに、デジタルへと変換している。
スポーツ選手を追いかけた何万枚の写真、日本、世界と旅したときの何万枚の写真。
雑誌の表紙、グラビア、TVのスチールで使われた写真も何枚もある。
ある意味、写真は自分の生きてきた旅の証(あかし)だと思う。
おもしろいもので、ボクシングの写真を例にあげると、デジタルよりフイルムで撮った写真の方がいい写真が撮れている。
いや、それはピンがきているとか、技術的なことではない。
魂といったらいいのか…当時の自分の気持ちが焼き付いた、そんな写真だ。
デジタルはリング下でシャッターを切るとき、何百枚もシャッターを押せば連続で撮ることができる。
だが、フイルムは36枚。
ぼくの場合、300ミリ、35ミリ、70〜200ミリのズームを取り付けた3台で撮っていたのだが、メインは70〜200ミリのズームレンズだ。
1Rの3分で36枚をどう撮るか。インターバルの1分で巻き戻し、フイルムをセットする。
残り30秒を切れば、本来なら10枚残らない状況でシャッターを切っている。
だが、たとえばずっと追いかけ、撮り続けた世界チャンピオンになった浜田剛史の場合、世界を撮った試合も含め、3分9秒KO勝ちの試合が3度ある。
その3度ともKOシーンはちゃんと撮れているし、ラストの場面でのシーン、つまりラスト15秒で15枚以上のフイルムを残してシャッターを切っていた。
そうなんだ。
あのフイルムの時代、ぼくは大事な試合はボクサーと同じように緊張し、世界戦では「君が代」を聞きながらボクサーと同じようにからだを動かし、精神を集中させていた。
だからリングサイドで闘う意志を持ってシャッターを切っていたんだ。
闘う意志とは、その試合の流れに、その試合の空間に完全に入って、ボクサーの呼吸を感じながら撮っていたということだ。
だから写真に気持ちが入っていく。
だから気持ちの入った写真が撮れていく。
デジタルは同じ気持ちではあるのだが、どこかで自分の中に油断を持っている。
そう、シャッターを切りすぎてしまっているのだ。
だからかも知れない。
最近、自然の写真が増えている。
気持ちを撮る。
一枚一枚呼吸で撮っている。
そういった撮り方をしている。
ちばてつや先生に言われたことがある。
「田中さんのメモは写真だね」
言われて気づいたのだが「そうだ」と思う。
ちば先生はメモに、ふとした目の前のこと、気づいたことを文字で、絵で描き、それをマンガという形にしていっている。
ボクの場合は、シャッターを切り、そこで感じたものが言葉になり、絵になっていく。
ときには音楽にもなっていく。
自分の描いたもの、書いたものはよくリアルと言われるのだが、それは現場に立ち、その風景や風、臭いを感じシャッターを切ったところから始まるのだから、そうなるのだと思う。
それは「創る」のボクのやりかたであり、それは「生き方」だとも思う。
そしてその生き方は、ちゃんとフイルムに焼き付いて残っている。
|
|
|
| | 2012年4月29日
大駱駝鑑の舞台を見に行った。
感情が奥底から絞り出されるよな、ゾロリとした快感と、文字で書けばそういうことなのか。
とにかく快感の舞台だった。
舞台の終わった楽屋では、憧れの麿赤兒さんにも会えて、何か20代の尖った鋭い感覚を持った気持ちの風が吹いてきた。
大駱駝鑑を始めてみたのは、80年に京都の曼殊院で見た「盤船伽藍」の、それまで感じたこよのない、まるで宇宙を感じる自然の中の生きた舞台でのパフォーマンスだった。
圧倒される感覚…
そう、あのころは、そんな感情を魂から揺さぶられる表現に夢中だった。
マンガも、絵も、音楽も、芝居も、何か魂が惹きつけられる「感じる」が「感動」だった。
どう表現したらいいのか、感情と感覚で感じるものが面白い。
そう、まさにブルース・リーの言った名言、「Don`t think Feel」だ。
考えて作られたものより、感じて生まれたもの。
たとえば、そういった「感じる」で、夢中になり大好きだった表現者を上げていくと、「寺山修司」「つげ義春」「あすなひろし」「上村一夫」「永島慎二」「真崎守」「宇野亜喜良」「横尾忠則」「唐十郎」「佐藤信」「藤田敏八」「荒木経惟」「米倉斉加年」「萩原健一」「赤瀬川原平」「神代辰巳」「石井隆」「辰巳ヨシヒロ」「麿赤兒」他、まだまだいっぱいあるのだが、とにかく「考える」ではなく、「感じる」ことで大好きになった表現者たちだ。
こういった新しい表現は、何か身体の奥から沸騰するような快感を得ることができるとともに、自分もそうなりたいと、「創る」に対する身体の中での沸騰が起こり始めてくる。
今の自分が創ることで生きてきたのは、間違いなくこういった表現者たちの作品を見て感じて育ったからだ。
だがそういった新しい表現は、原稿料のもらえる場所ではどんどんとなくなっているし、メジャーの中で面白がれる場所もなくなっている。
といって、そういったものを創る作家がいなくなったとか、そういうものに興味を示さなくなったのかと言えば、ぜんぜんそういったことはない。
たとえば、ぼくの周りの学生たちにしても、つげ義春、上村一夫、寺山修司 などの、ぼくの研究室にあるマンガ、書物、映像を夢中で面白がって、刺激を受けて、快感を感じて見ている。
そんな学生たちを見ていて、また、自分と同じ臭いで集まってきているアーチストたちと飲みながら、語りながら、あの「感じる」感覚で作品を生み出したいと、今の時代での「感じる」を創りたいとみんな心に秘めている。
ならば、ならばだ。自分が面白がれる場所がないなら、その場所を創ろうではないか。
そう、メジャーな場所で作れば大きな影響力を生み出せるではないか。
ここ何年かそういう思いで動いてきて、特にデジタルの場所では形になってきている。
だから、ここまでがんばれるし楽しい。
面白いもので、そうやって動いていると、同じ臭いのもった人たちが集まり、また、自分が影響をうけ、憧れた人たちにも出会うことができている。
それも大きな力になっていくというわけだ。
そう、今回も「感じる」で、また会いたい人に会えたことに感謝。 |
|
|
| | 2012年3月30日
「日々を最後の日として生きよ。その日は誤ることなくやってくる」
スティーブン・ジョブズの言葉なんだけどね。
この言葉を知ったとき、何か「あぁっ」って思ったんだ。
その「あぁっ」って、「人は必ず死ぬ」ってことなんだけどね。
つまりは、それは「生きる」ということは「時間」だと、「時間というものは命」だって、そう感じさせられた言葉だったんだよね。
ジョブズのこの言葉を知ったのが、3.11の後なんだけど、3.11があったからこそ強烈に心にとどまった言葉のように思うんだ。
きっとだれもがあの日を境に、大きく「何か」が変わったように思うんだ。
その「何か」は、ひどくガッカリする政治の終わったようなこの国の一年だったけど、でも、そんなこともあったことで、今までのような「与えられる」に期待しなくなり、ひとりひとりが自分で変化する視線を少しずつだけど考え始めた「何か」、そんな気がしてるんだ。
つまり「何か」はそれぞれの「生きる」なんだけどね。
ぼくの場合は、24歳のとき音楽で挫折を味わい、ホント、すべてを捨てて東京へ出てきたとき、「何か」を求めて大事にしてきた言葉を再び3.11の後に思い出してね。
その言葉は、ジョン・レノンの言葉。
「心を開いて“Yes”と言ってごらん。すべてを肯定してみると答えがみつかるもんだよ」この言葉なんだけどね。
思い返してみたら、“Yes”で生きてきたことで、マンガを描き、イラストを描き、写真を撮り、文章を書き、原作を書き、デジタルで新しい表現の作品を創り、つまりは興味あること何でもやってきて、幸せなことに少しだが、生きていける収入になってここまでやってきたと思ってるんだ。
でも、忙しいとか、今更とか、できないかもとか、当たり前だけど踏み出さなかった“No”もずいぶんあると思ったんだ。
でもね、「時間というものは命」だと思ったら、すごくそのことがもったいなく思ってね。
日々、いろいろな人が声をかけてくれる。
「Yes」と言えば、そこから新しいことが始まり、また新しいいろいろな人と出会っていく。
決められた時間の中で、その中で「無限」の気持ちで「Yes」と答えようって、それが3.11からの決めていること。
音楽もだからまたやりはじめている。
たしかに凄く忙しい日々だけど、そのひとつひとつがホントに面白くて、そこからいくつもの新しい「始まり」も生まれてきている。
ちばてつや先生がね、昨年、3.11のあと、ぼくがチャリティもあって、忙しくて忙しくって、何ヶ月も睡眠時間が一日3時間なかったときに、そんなぼくに対して言った言葉があるんだ。
「いいね」という言葉。
ガンバレとか、そういった言葉じゃなく「いいね」だよ。
その「いいね」は、“思い切り生きてるね”という言葉。
うん、とにかく今の日々を、「いいね」の時間で歩んでいくと決めている。
※3月31日(土)東京銀座のジェイトリップアートギャラリーで、16時より、アートと音楽のコラボライブをやります。
今回は、ミュージシャンとしてコラボします。
詳しくは http://www.jtrip-118.com/
|
|
|
| | 2012年2月10日
“祭りのあとの淋しさが〜いやでもやってくるのなら〜”
ふとしたときに、よくこのフレーズを口ずさんでいる。
“よしだたくろう”の「祭りのあと」という曲だ。
72年の高校一年の夏、友人から“よしだたくろう”の「元気です」といアルバムを借りて聴かせてもらい、その中に入っていた曲だった。
今もその歌詞を口ずさんでしまったこともあって、「あぁ…そうなんだよな」と思うことがありこの日記を書いている。
祭りというのは、祭りの前の、早くその日が来ないかという期待の中でのワクワクする日々があり。
そして祭りはほんの一瞬の眩しい時間。
それが終わったとたんに、いや、終わりを感じたそのときから淋しさが胸を押さえつけてくる思い。
締め付けられるような何とも言えない淋しさ。
何かそんな淋しさがこの曲と重なって、高校一年で始めてこの曲を聴いたとき、何かを感じ取ってしまったわけなんだ。
そう、夏休みも同じだったな。
夏休みの一週間前のワクワク感。
そして夏休みの終わろうとしている一週間前の、夏の終わりの苦しいほどの淋しさ。
自分のHPのタイトルに、「毎日が真夏」と付けたのも、終わりのない真夏の日々をつづけたいとの思いからだったんだ。
そういったことを考えて、なぜこの「祭りのあと」という曲が心にズシリと染みこんでしまったのか…今も口ずさんでしまうのか…
もちろん、いい曲だからなのだ。
だが、それ以上にどうもぼくは「祭りのあと」という言葉に惹かれていたようだ。
祭りが終わるということは、それは“日常”に戻ることなんだと思う。
終わったときから、“日常”に戻ってしまうことへの、“特別(祭り)”が終わったことの淋しさ。
それが嫌だった。
ならば、ならばだ。
祭りをづっとつづけていければどんなに楽しいんだろうと思ったわけなんだ。
祭りが終わっても、次の祭りと永遠につづいていく日々。
ぼくはいつも“旅”のように生きたいといつも言ってきた。
“旅”というのは、つねに出会いの日々。
人だけじゃなく、見知らぬ土地や国の海や、山、森といった自然や、音、風、臭い、食といったものもそうだ。
毎日が出会いならば、それは“特別(祭り)”の日々になる。
出会いから生まれ、自分の中から沸いてくる、書いたり、創ったりする行為もすべてが旅のつづきだと思っている。
つまり“旅”という生き方には、“日常”がないという生き方だ。
終わらない“祭り”をつづけるという生き方。
そう考えると、心に「祭りのあと」の風がいつも凪がれていて、それで口ずさんでしまっていたのは、ぼくにとっては、よしだたくろうの「祭りのあと」は、“日常”ではなく、自由を求める気持ちの曲だったのだと。
そう思う。
“祭りのあとの淋しさが〜いやでもやってくるのなら〜祭りのあとの淋しさは〜たとえば女でまぎらわし もう帰ろう もう帰ってしまおう〜寝静まった〜街を抜〜けて〜” |
|
|