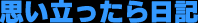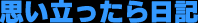| | | 2016�N12��31��
�u�ǂ�������v���Ƃ��Đ�������̂ł����H�v
�w���ɂ���������������悭������B
���̂Ƃ��ڂ��͂��������邱�Ƃɂ��Ă���B
�u����ɂł��ł��邱�Ƃ��A����ɂł��ł��Ȃ��������v
 
 
������O�̓������B
�u����ɂł��ł��邱�Ɓv�ɂ������Ă܂łق����Ǝv���Ă����l�͂��Ȃ��B
�u����ɂł��ł��Ȃ��v�������������҂́A�u����ɂł��ł��Ȃ��v�u�́v��g�ɂ�������B
�u����ɂł��ł��Ȃ��v���炱���A�l�͂������Ă܂ŁA�ق����Ǝv���Ă����B
���Ƃ��A�X�|�[�c�I��Ȃ�A�u�́v�Ƃ́u�����́v���Ǝv���Ă���B
�u����ɂł��ł��邱�Ƃ��A����ɂł��ł��Ȃ��������v�Ƃ������Ƃ́A�싅�Ȃ�150�`�ȏ�̃{�[���𓊂��邽�߂ɂǂꂾ���̂��Ƃ��A�ǂꂾ���̐����������Ă������B
1�N��2�N����Ȃ��B10�N�ȏ�̎��Ԃ��Ȃ���Ύ�ɓ���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��͂��B
���́u����ɂł��ł��Ȃ������́v���ԂƔw�i�������āA�����ɂ́A�Ƃ��Ă����̓���������Ƃ��ł��Ȃ��ƁA�������A���h���A���̐������ɗE�C�����炤�B
�����Ď����̓��ŁA���̑I��̐����Ă������́u�����́v���������ƗE�C�����炤�������킯���B
�����͂��̓��Ȃ�u����ɂł��ł��邱�Ƃ��A����ɂł��ł��Ȃ��������v���Ƃ�������ƁA�l�́u���v������B

�u�Ȃ�������̂��v�Ɩ����A�ڂ��́u��������������v�Ɠ����邾�낤�B
�������͕K�����ʁB
�����玀�ʂ܂Ő����������Ɛ����Ă����B
���ꂪ�u�����́v�Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
�����Ă���u���v�̘A���ł���B
�ł�������u���v�ƂƂ炦���A�u���������z����ΐ����ł���v�ƍl�����Ȃ�A�u���v�����邩�炱���A���́u���v���傫����Α傫���قǁA�܂����X�u���v�ł�������l��萬���ł���B
���͂܂��Ɂu���������v�Ȃ̂�������Ȃ��B
��������낤�Ƃ���A������O�����u���v�̓O���R�̂��܂��̂悤�ɕt���Ă���B
�������Ȃ��ł���A�������ɂ�������u���v�͕t���Ă��Ȃ���������Ȃ��B
�����A����ōK���Ȃ̂��낤���B
�u���v�Ɠ����l�������l�ƁA�������l�ł́A���ʂ܂ł̐������܂������Ⴄ����������ƂɂȂ�B
2016�N�A�����Ɂu����ɂł��ł��邱�Ƃ��A����ɂł��ł��Ȃ��������v���Ƃ��ł����̂��₤�B
�uYes�I�v
  |
|
| |
| | | 2016�N11��29��
���������Ԃ�O�A��w�̂���F�s�{���瓌���A��Ԃ̒��ŁA���Ă�搶�Ƃ���Șb���������Ƃ�����B
�w�������̘b�����Ă���Ƃ��A�u�w�������͏�������āA�݂�ȕs����������Ă����ˁv�B
���ΐ搶�͂Ԃ₫�A�����āu�l�͂���ł��s�����̂ɂˁv�u�ڂ������ĕs���͂��������Ă邩��ˁv�ƌ��t���Â����B
�u�s���v�����邩��l�́u���v�������ɐ����悤�Ƃ���B
�����A�w�������Ă���ƁA�u���v�ł͂Ȃ��A�u�����v���茩�ĕs���Ɋ����Ă���悤���B���ΐ搶�́u�Ȃ��w�������́u���v��K���ɐ����Ȃ��̂��낤�v�u���A�K���ɐ��������̂������A������������Ă���̂ɂˁv�B
�u�������̃W���[�ł��ˁv
�ڂ��͂��ΐ搶�̌��t�ɂ����������B
�u�����A��W���[�́u���v��K���ɐ������L�����N�^�[����������ˁv
 �����ȂB �����ȂB
�������̃W���[�ɖ����ɂȂ����̂́A����������̃}���K�ɖ����ɂȂ����̂́A�ԈႢ������W���[�́u���v���A�u���v���������ĕK���ɐ����Ă��鐶�����Ɏ䂩�ꂽ���炾�B
�����������ƂȂ̂��B
�W���[�͖ڂ̑O�́u���v�����ɐ����Ă����B
�{�N�V���O��ʂ��Ėڂ̑O�́u���v�ɏo��A�͐ΓO�Ƃ����ڂ̑O�́u���v�ɏo��B
���́u���v���邱�Ƃ����A�u���v���邱�Ƃ��������ׂĂ̐������Ő����Ă���B
������A�u���v�����邷�ׂĂ̗͐�����ŃW���[�́A�u���v���������{���{���ɂȂ��������B
�����܂��V���ȁu�J�����X�E���x���v�Ƃ����u���v���\��A�u���v���͂��߂�B
�����čŋ��́u�z�Z�E�����h�[�T�v�Ƃ����u���v���\��邱�ƂŁA���́u���v�ɂ��ׂĂ��q���āu�^�����ȊD�v�ɂȂ�܂Łu���v���Ă������ƂɂȂ�B
��W���[�͐��E�`�����s�I���ɂȂ�Ƃ����u�����v��ڎw�����̂ł͂Ȃ��A�u���v�������A�u�ڂ̑O�̖ړI�v�̂��߂ɁA�����u���ׂ����Ɓv������K���ɐ����A�����A���������E�^�C�g���}�b�`�܂ōs���������j�̘b���B
�l�́u���v��K���ɁA�����ɐ����āA�ӂƗ����~�܂�U��Ԃ����Ƃ��A�u�����A�����܂������v�ƁA���ꂪ�u�������܁v�̂͂����B
��������̂ł͂Ȃ��A�u���v����B
�����ĉ��߂Ďq���̍����疲���ɂȂ�����W���[���l���Ă݂�ƁA�W���[�͎������u�S�v�Ő������j�������ƁA�N����d�˂Ă͂����茩���Ă���B
������߂�Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��Ύu���Łu���E�`�����s�I���Ȃ�Ă܂��Ȃ�Ȃ��v���v�����Ƃ���A����͖{���ɐ��E�`�����s�I���ɂȂ�Ȃ��Ă�����߂��̂ł͂Ȃ��A�P�Ɂu�S�v��������߂������̂��Ƃ��B
�l�́u�S�v�ɂ���āA�u���v��������߂Ă��܂��B
�W���[�́u�S�v�ł�����߂Ȃ������B
������u�^�����ȊD�v�Ƃ������t���L�����N�^�[���琶�܂ꂽ�̂��Ǝv���B
�u�������̃W���[�v�͏��N���ŋ��߂���u�����v�ɂ����āA���C�o���Ƃ��ďo�Ă���A�͐ΓO�A�J�[���X�E���x���A�z�Z�E�����h�[�T�Ƃ���ɂ��u�����v��[�߂Ă��Ȃ��B
�����A�u�����v���Ȃ�������W���[�ɁA������������ɂȂ����B
���C�o���Ɂu�����v�̂Ȃ����N���Ȃǂ܂����肦�Ȃ��͂��Ȃ̂Ɂc
���̍ɂȂ��āA����Ɓu�����v�̈Ӗ����킩�����C�����Ă���B
�{���̏����Ƃ́A�u�S������Ȃ��v���ƁB
�����������Ƃ��B
|
|
| |
| | | 2016�N10��30��
��w�Ŗ����z�z���Ă���u�}���ق����v�Ƃ������q������B
��w�̋������������S�ɁA�w���������u�v���v�������Ă���B
�u�}���ق����v�Ƃ������q�̃^�C�g������킩��悤�ɁA�����ɂƂ��Ắu�{�v�ɑ���u�v���v���B
�������猴�e�𗊂܂�A�u�{�v�̂��Ƃ��l���Ă݂��B
���Z�̂Ƃ��A�}���قŖ��T7���ȏ�̖{����Ă����̂�����A�P����1�N��350���قǂ��{��ǂ�ł������ƂɂȂ�̂ŁA���͏��������Ă͂��邪����10���ȏ�͕K���ǂ�ł���B
�܂��A�Q��Ƃ��ɕK��1���Ԃقǖ{��ǂ�ŐQ��Ƃ����̂��A�������\�N���Â��Ă����킯������A�l�����疜�̐����ԈႢ�Ȃ��ǂ�ł��邱�ƂɂȂ�B
����ȕK�������ǂ�ł���u�{�v�̂��Ƃ��A���e�̈˗����čl���Ă݂��B
�����z�z���q�ɏ��������e�Ȃ̂ŁA���́u�v���v�����������e����L�ɂ��ڂ��Ă����B

�^�C�g���@����̖{���u������v�̓�����ɂȂ�
�l��������Ƃ������Ƃ́u���v������������̂��H
�ڂ��́A�l�͎��ʂ܂ŁA�Ō�̂��̏u�Ԃ܂Łu�m�肽���v�Ǝv��������u�S�v���Ɗ���������B
�܂�A�u�m��v�Ƃ������ƂŁA�l�́u�����v���A�u������v�Ƃ��������͂����܂�Ă���B
�{�Ƃ������̂́A�����邽�߂́u�m�肽���v�̓�����ł���B
�����̐l����U��Ԃ����Ƃ��ɁA�ԈႢ�Ȃ��A���́u������v�ƂȂ����u�{�v�����݂���B
����������B
������ƂȂ����{�͂���������B
�ڂ��������̐l���̃o�C�u���Ƃ܂Ō����Ă���{�́A�ԈႢ�Ȃ����w�Z��5�N�i1968�N�j�̂Ƃ��ɏ��N�}�K�W���ɘA�ڂ���A�o������u�������̃W���[�v���B
�����ă��A���ɁA��ƂƂ��đ傫�ȓ�����ƂȂ������������B
��؍k���Y�́u��u�̉āv���B
�{�N�V���O�̃m���t�B�N�V�����ł���B
�V�˂ƌ���ꂽ�{�N�T�[�A�J�V�A�X�����ƁA���X�̐��E�`�����s�I������Ă��G�f�B�E�^�E���[���g�g���[�i�[����l�O�r�Ő��E�`�����s�I����ڎw���A���̎p���A���A���^�C���Œǂ������Ă����B
����ǂ�������{�N�T�[�ƃg���[�i�[�ƁA���̓������ԁA��ԁA��C���̒��œ��X�����A���̉Q�̒��ŁA��ގ҂ł����؍k���Y���g���A���m�~�h�������������̃}�b�`���[�J�[�Ƃ��āA�����ăZ�R���h�ɗ����^�C�g���ɒ���ł����B
�ڂ������̖{�Əo������̂�24�̂Ƃ������A�u����ȍ�ƂƂ��Ă̐������������������I�v�ƏՌ��������A�����ăy�[�W���߂���h�L�h�L���́A���܂܂ŏo��������Ƃ̂Ȃ����̂������B
���ʂ������Ď�ނ��A�`�����i�ł͂Ȃ��B
��ގ҂̌��ʂւ̕��݂̒��ɁA��Ǝ��g���g��u���A��ގ҂Ɠ������������A�����Ď���҂Ɠ����u�o��v�������Đ����čs�����ł��̍�i�͏�����Ă����B
�u�����c�v�ƁA�����āu���܂��v�Ɠǂ݂Ȃ���}������Ȃ�����N������i�������B�ǂݏI�������ƁA�u�m�肽���v�Ǝv�����B
��ƂƂ��Ă����Ƃ����Ɛ[���A�u���������v�Ǝv���l�Ԃ̉��̉��̉��܂ŁA���̌ċz�̙����܂Œm���ď��������Ǝv�����B
���ꂩ��4�N��A�ڂ��͂ЂƂ�̃{�N�T�[�Əo��A���̃{�N�T�[��m�邽�߂ɁA���������߂̍Œ���̎d���������A�����A���̃{�N�T�[������������X���߂�����2�N�������邱�ƂɂȂ�B
���X�{�N�T�[�̖���ǂ�������2�N�ԁB
�ǂ������Ă������X�ŁA�{�N�T�[�̖����A�������g�̖��ƂȂ����Ƃ��A�ċz�̙�܂ł�����܂łɂȂ��Ă����B
�����������Ƃ͂��̃{�N�T�[�̂��Ƃ����ƂȂ�A���̎v���������A�B��A�`���A�}���K�A�O���r�A�A�m���t�B�N�V�����ƃ{�N�T�[�̐������܂��i�s�ŎG���A�P�s�{�ATV�ō��i���n���Ă����B
�{�N�T�[�̐��E�^�C�g���}�b�`�̂Ƃ��́A���̃{�N�T�[�ƂƂ��ɁA�����u�����v�Ȃ��ł͎v�������܂炸�A���E��̃|�X�^�[�̃C���X�g���W�����痊�܂ꂽ���Ƃ���A�{�N�T�[�ƂƂ��Ɍ��ʂ��Ȃ���A�u���~�b�g���Ȃ���Ό��e���͂���Ȃ��v�ƁA�ЂƂЂ����A�{�N�T�[�ƂƂ��Ɋo��������Đ����邱�Ƃ̂ł������Ԃ������B
���̃{�N�T�[�A�l�c���j�͐��E�`�����s�I���ɂȂ����B
���̏u�Ԃ��v���o���ƁA���܂ł��g�̂��k���o���B
�ƂĂ��Ȃ��Z�����Ԃ�����2�N�ԂŁu�m��v���ƂƂȂ����B
�����ȂB
�u��u�̉āv����n�܂����u�m�肽���v�̔Z�����Ԃł���B
���ꂩ�琔�\�N�c��؍k���Y�̖{���ƁA�����ɏ����ꂽ�G�b�Z�C�ƂƂ��ɁA�ڂ������ʂ��Ȃ���`�����A���E�^�C�g���}�b�`�̃C���X�g���`����A�ڂ��Ă����B |
|
| |
| | | �g�����c���Ƃ́A�ł��������̂ł͂Ȃ��B
�ł��m�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��B
����́A�ω��ɍł��悭�K���������̂ł���h
�_�[�E�B���̌��t�ł���B
������19���A�����ۉ�c��ōs��ꂽTGSW�Z�b�V����(���E������̌����҂��W�܂��Ă̌�����j�ɌĂ�āA�Ԃł��ւ��Ă�搶�ƌ������Ă���Ƃ��A�搶�����̌��t���ӂ��ƂԂ₢�Ă����B
�����Ȃ̂��B
���͎���̕ϊv�̂Ƃ��ł���B
���܂܂ł̏펯�����Ƃ��Ƃ�������Ă��Ă���B
�}���K�����āA�}���K�͍��q�œǂނ��̂Ƃ����펯�ȂǁA����10�N�ł܂������ς���Ă��܂����B
�܂�͏펯�Ɏ����Ă�����A�u���v�ł���n���̉\����ے肵�Ă������B
�_�[�E�B����200�N�O�ɐ��������R�Ȋw�҂Ȃ̂����A���̌��t�͍ŋ߂Ō����A�X�}�[�g�t�H�����v�������ׂĂ��炦��u���̒ʂ�v�������Ă��܂��B
iPhone�����܂�Ă���܂�������10�N�ł���B
�����A������10�N��iPhone�͎���̒��S�ɂȂ��Ă���B
�����ƌ����A�A�b�v���ƃO�[�O���̎���ɂȂ��Ă���B
���̕ϊv�̒��ɂڂ������͂���B
�Ȃ�Εω��ɓK������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��B
�X�}�[�g�t�H���̒��̃A�v�����g����悤�ɂȂ�Ƃ����K�����Ȃǂł͂Ȃ��B
�X�}�[�g�t�H���Ƃ����\�����L�����u���m�v�ŁA�V�����\����ł����́B
���ꂪ�ω��ɂ����Ƃ��悭�K������Ƃ������Ƃ��B
����Ɏg����̂ł͂Ȃ��A�����n���Ă������̂������c��Ƃ������Ƃ��B
�ڂ��͍��A����̕ω��̒��ŁA�f�W�^���̒��ł��낢��Ȃ��̂ݏo�������������Ă���B
�������炱���ł���A����̑n���B
���Ƃ����ăf�W�^���ł��ׂđn�낤�Ƃ����l���ł͂Ȃ��B
�f�W�^���őn��Ȃ����́B
���Ƃ��Ύ��R�ł���B
���܂܂ł́u�֗��v�Ƃ����l�Ԃ̘����Ŏ��R���Ă����B
���H����邽�߂ɁA���S�N�A����N�̎��R��ׂ��Ă��Ă���B
���̎��R�̓f�W�^���ł͑n��Ȃ����A���S�N�̎��́A���S�N�̎������Ȃ�����炽�Ȃ��B
���R�����̂܂܂Ɂc
����A���R�̒��Ő����Ă������߂Ƀf�W�^���𗘗p����̂��A���̎���Ȃ̂��͂Ȃ����낤���ƁA�ڂ��͍l���Ă���B
���A���R�̈���Ȗ̓ߐ{�Ői�߂Ă��邱�Ƃ�����B
���R������A���̎��R�̒��Ŗ������������Ă��炦��V�n�������ɂ͂���B
���̓V�n�������Ă��炤���߂ɁA���A�����A�J�����Ă��鎩�R�̒��ő��Â��u�}���K�v�ł������l���Ă��邱�Ƃ�����B
���̒��̕ω��̒��ŁA���̋Z�p�����܂�Ă������ł��炱���A���R�����ɁA���R�̒��Ő����čs���鐶�����B
���̓��L�ł����x�������Ă����AioT�AAR�AAI���L�[���[�h�́A�����Ƀ}���K�̃L�����N�^�[�Łg�S�h���Ȃ����V�X�e�����B
�܂��܂��\�ɏo���܂ŏ����Ȃ����Ƃ��炯�Ȃ��̂ŁA��̓I�Ȍ`�͏����Ȃ����A�Ƃɂ������́A�ω��ɍł��悭�K�������A�u���v�u�����v�Ő����Ă��邨�Ƃ��l���A�n��ȓ��X�𑗂��Ă���Ƃ������Ƃ��B |
|
| |
| | | 2016�N8��30��
���N�����m�Ŗ��N�s����u�܂b�q���v�ɎԂōs���Ă����B
�����ւ̋A�蓹�́A���̓��̋C���Ńn���h�����A�C����������A�R����������c
���߂Č��鎩�R�̕��i�ł�������A���߂Ă̊X�Ƃ̏o��̖����B
�������N���ԂŌ��������m�́A�ڂ��ɂƂ��ẲĂ̗��ɂȂ��Ă���B
���ƌ����Η��ɏo��Ƃ��A�ڂ��̃J�o���̒��ɂ͐����̖{�������Ă���B
����ƂƂ��ɁA�h�L�������^���[��f���^�悵���܂܂ł܂����Ă��Ȃ���i���ADVD�ɏĂ��āA��������̗F�Ƃ��Ă������N���������悤�ɂȂ����B
�Ԃŗ��ɏo���ꍇ�A���̓m�[�gPC��3��Ԃɐς�ł���B
�d���Ɋւ���p�r�Ŏg�������Ă��邻�ꂼ���PC�����APC�����������悤�ɂ����Ă���A����ŐQ��O�ɖ{�ł͂Ȃ��ADVD�����邱�Ƃ������Ȃ����B
����ł͖{�ɂ���ADVD�ɂ���A����Ƃ͈����������`���Ă��A�����̒��ɋ�����i�Ƃ̏o�������B
����́uNHK�X�y�V�����A�~���N���{�f�B�̋`���̃W�����p�[�v�������B
�E�����`���̑��蕝���ёI��ł���}���N�X�E���[�A�́A���N�̏�Q�җ��㐢�E�I�茠�ŁA���E�V�L�^�W���[�g���S�O�Z���`��A�����h���ܗւ̋����_���L�^�����I������グ�Ẵh�L�������g�������B
���I�̃I�����s�b�N��ڎw�����A�`�����W�����v�ɗL���ɓ����̂ł͂Ȃ����ƁA�I�����s�b�N�o��͊���Ȃ��������A���̃h�L�������g�ł́A�Ȋw�Ńg�b�v�A�X���[�g�Ɣ�r���A���[�A�I��̓��̂�����҂̓��̂���������ƂƂ��ɁA�̂̈ꕔ���������ƂŔ��B�����m��ꂴ��ؓ��B
����Ɍ���҂ɂ͌����Ȃ��]�̓����B
�`����̂̈ꕔ�̂悤�ɑ��関�m�̔\�͂̊J�ԂƁA�܂��Ƀ~���N���{�f�B���������Ă����B
����҂̓��̂���ؓ���n��グ�邽�߂ɂǂꂮ�炢�̂��Ƃ����Ă������B
�g�̂̈ꕔ�������A�����₤���߂ɂ���ꂽ�ؓ��A�����Ĕ]�̓������Ƃ��ɁA�l�Ԃ̉\���������Ă����B
�܂��ɐl�Ԃ̌��E�������̂�n��グ�����炱�������Ă��鐦�݁B
���[�A���ԑg�̍Ō゠����ł������������t������Ă���B
�u����ȏ͋����Ȃ�`�����X��������Ȃ��v
�u�ڂ��͂������牽�������݂����v
�����c�Ǝv���B
�܂��ɂ����ȂA�u����v�͎����������Ȃ�`�����X�ȂB
���t���S�ɋ����B
�����ă��[�A�͌��t�������Â���B
�u�ǂ��܂ł������֔�т����v
�u�ڂ��̓��̂̌��E���ǂ��ɂ���̂��m�肽���v
�u���E�ɒH�蒅���܂Œ��݂Â������v
�l�͂���ł������̌��E��m�肽���Ǝv���Ă���͂����Ɗ����Ă���B
���܂ꂽ�Ԃ�V�́A���ׂĂ̎��Ԃ𐬒����邽�߂ɐ����悤�Ƃ��Ă���B
�����̉\����T��A�ƂĂ��Ȃ������Ői�����Ă����B
���ꂪ�{���́u�����������́v�̖{�\�̂͂��ł���B
�A�X���[�g�Ɍ��������Ƃ���Ȃ��B
�}���K�ݏo�����́B
�ŋ�����������́B
AI������������́B
�����̂܂��ɂ��A�����̌��E��m�肽���Ɓu����v�ɗ����������Ă���l���������l������B
�ʂ����Ăڂ��͂ǂ��Ȃ̂��B
�����͊ȒP���B
�u����ȏ͋����Ȃ�`�����X�v
���˓��C�̊C�����Ȃ���A�����̖ڂ̑O�́u����v�́A�����������Ȃ��`�����X�Ȃ̂��ƁB
����ŏo������A�ЂƂ̃h�L�������g����́i�`�����X�j�����炦���A�����r���̉Ă̋L���B |
|
| |